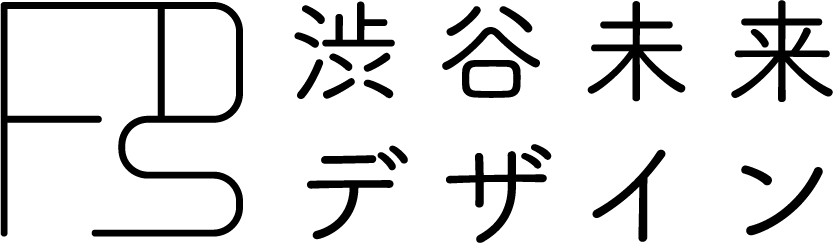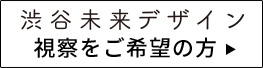最新の都市データの事例共有と一般社団法人渋谷未来デザインの会員間の連携を図るオープンな勉強会を開催しました。
最新の都市データの事例共有と一般社団法人渋谷未来デザインの会員間の連携を図るオープンな勉強会を開催しました。
「都市データ勉強会」は、一般社団法人渋谷未来デザインが主催でオンライン、オフラインのハイブリッドで年3回実施を予定しています。今回の「都市データ勉強会」では、都市が直面する現代的課題を多角的に捉え、データを基盤とした課題解決の可能性について活発な議論が行われました。
概要
「大都市における熱中症対策とその影響」」
2025年6月18日(水)@GAKU
開会挨拶
開会にあたり、2019年に始動した「日陰マッププロジェクト」を例に挙げ、気候変動対策の重要性を改めて強調しました。
当時は都市空間における「暑熱リスク」への意識がまだ高くはなかったものの、継続的なデータの蓄積と可視化が、都市政策に大きな示唆を与えつつあると語り、「今後も都市データの収集と活用を加速させたい」と意気込みを示しました。

基調講演
一般社団法人渋谷未来デザイン 代表理事・東京大学工学系研究科 教授の小泉先生に「社会経済的大転換に対応した持続可能な都市のデザインを考える」をテーマに講演いただきました。産業革命以降の都市構造の変遷を紐解きつつ、現代都市が抱える複合的な課題に言及しました。
小泉先生は、気候変動、人口減少と高齢化、経済のグローバル化と地域格差の拡大など、多様な問題が複雑に絡み合う現状を、歴史的視点から分析。特に「都市の成長とともに生まれる課題を、データを用いていかに可視化し、次の都市デザインへと結びつけるかが重要だ」と強調しました。
企業からの取り組み共有
ダイキン工業株式会社からは、SHIBUYA GREEN SHIFT PROJECTの最新状況が共有されました。
気候変動への適応策として、都市空間の暑熱環境を緩和する屋上緑化、最新の空調機器に内蔵されたセンサーを活用した高精度な温度モニタリング、さらに地域住民や来訪者が自由に涼める「クールスポット」の設置事例など、技術と現場を結ぶ多様なアプローチが紹介され、参加者の関心を集めました。
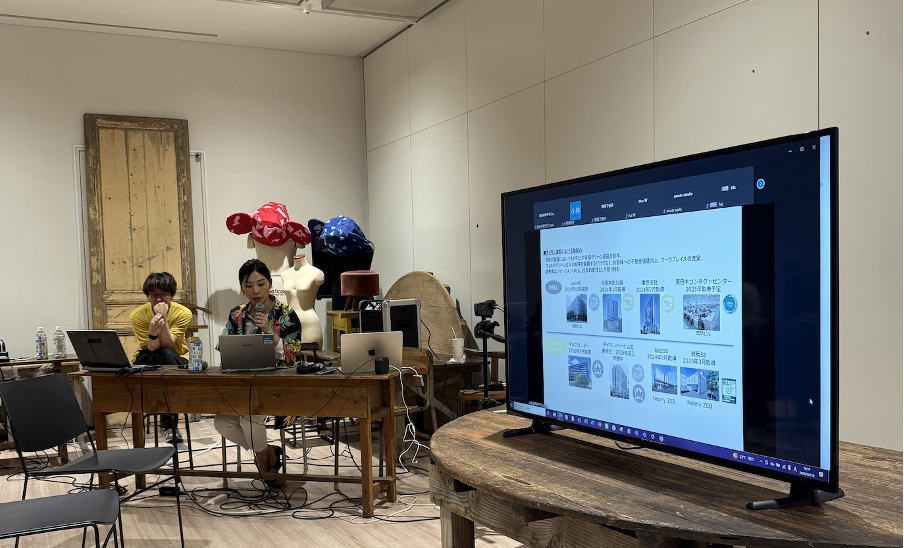
またカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社さまからは、渋谷エリアの来訪者分析データが発表されました。
2022年から2024年にかけての人流データをもとに、来訪者の世代構成やライフスタイルの変化、特に20代女性の増加や、文化・芸術イベントに関心を持つ層の割合の増加などが可視化され、都市空間の活性化に向けた新たな示唆が提示されました。

今後の展望
今回の勉強会を通じ、都市データが持つ可能性と、分野を越えた連携の必要性が改めて確認されました。
都市の持続可能性を実現するためには、単なるデータ収集にとどまらず、得られた知見をどう政策に生かし、市民の行動変容を促すかが問われています。
未来デザインでは、今後も企業・行政・市民を巻き込みながら、具体的なプロジェクトを形にしていくとともに、こうした議論の場を継続して設けていく予定です。
まとめ
本勉強会は、参加者一人ひとりが「都市の未来を自分ごととして考え、共に行動する」きっかけとなる貴重な機会となりました。
データ、テクノロジー、そして人の知恵とつながりが、持続可能な都市づくりを支える原動力になることを、参加者全員が再確認する場となりました。