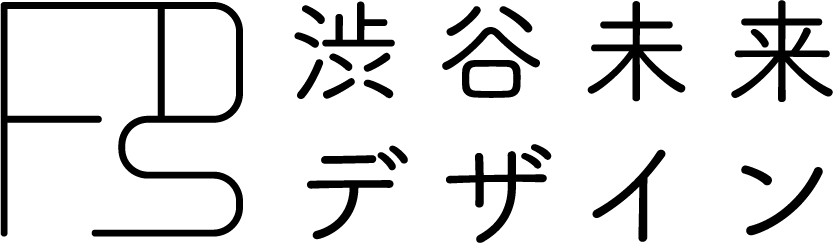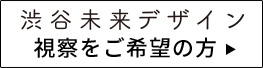渋谷未来デザインと一般社団法人SWiTCHが中心となり、脱炭素社会、生物多様性などサステナブルをテーマに産官学で議論をしてきた「Carbon Neutral Urban Design(CNUD)」。CNUDが定期的に開催している「環境ブランドMEETUP」は、環境先進のアイデアが詰まった現場をガイドする体験型交流セッションです。自社の環境への取り組みを深く伝え、共感を得て仲間を増やしたいと考えている、広報・ブランディング・営業担当者の皆様を対象に、ブランド戦略における「環境コミュニケーション」について対話します。
第3回目の「環境ブランドMEETUP」は「未来世代に向けての環境コミュニケーション編」として開催され、環境省 広報室の浜島直子様、株式会社博報堂 研究デザインセンターの根本かおり様にご登壇いただきました。
環境ブランドMEETUP Vol.3 〜未来世代に向けての環境コミュニケーション編〜
2025年3月12日(水) @ TENOHA 代官山
<登壇>
浜島 直子(環境省 広報室長)
根本 かおり(株式会社博報堂 研究デザインセンター 上席研究員)
佐座 槙苗(一般社団法人SWiTCH 代表理事)
冒頭の挨拶で、東急不動産ホールディングス株式会社の松本さんから、「企業がサステナブルな取り組みをすることは当たり前になった今、顧客やステークホルダーにどのように発信していくかを皆様と一緒に考えるきっかけにしたい」と今回のMEETUP開催の目的が伝えられました。また、今回の会場のTENOHA代官山について紹介し、施設の建築や生物多様性、食品ロスからの再生エネルギー活用等、TENOHA代官山がサステナビリティの発信拠点になることを紹介しました。

第1部は、環境省 広報室 浜島さんと株式会社博報堂(以下、博報堂)の根本さんの2名が、それぞれの取り組みの紹介をしました。
行政の広報は、政策の理解や浸透を促し、社会に定着させることを目的としています。浜島さんは環境省の具体的な取り組みの一例として、 「デコ活」や、こども向けパンフレット「環境税って何だろう?」の広報施策を紹介しました。また、企業向けの施策としては、AIを活用したWEBアンケートの解析やデータ提供を通じたマーケティング支援を取り上げ、さらに、教育者向けには、環境意識を高めるリーダーズ研修を実施し、次世代を担う人材の育成にも取り組んでいることを共有しました。
根本さんは研究デザインセンターが取り組む「未来洞察」の活動を通じた気づきを共有。冒頭で、現代において未来を楽しむ余白が減少しているという視点が提示され、若者世代の価値観や考え方について、データを用いて紹介しました。また、世代を超えた共創の事例として、産業共創/経済産業省の「GXリーグ 、社会共創/「Nature Positive Studio」、事業共創/「TOKYO TECH STARTUP STUDIO」を紹介しました。これらのプロジェクトを通じ、未来の不確実性に向き合いながら、多様で創造的な社会の構築が求められていることを伝えました。

第2部のトークセッションでは、今回のテーマ「未来世代に向けての環境コミュニケーション」について意見が交わされました。
『未来世代はどんな人?』のパートでは、まず「未来世代」の定義付けから。未来世代のイメージを参加者の皆さんに聞くと、「多様な価値観を持ち、表現豊かな世代でもある一方、期待値も高まっているため自分の意見を主張しづらい世代」といった声が上がりました。それを踏まえてふたりはこう語ります。
浜島「現代はSNSを活用し、自ら選択肢を作れる時代になりましたが、その一方で“選択肢を作らなければならない”というプレッシャーを感じている学生も多いと実感しています」
根本「ネガティブなテーマが取り上げられがちですが、年齢に関係なく“未来に何かを伝えたい”“未来を変えたい”と考える人こそが未来世代であってほしい」
続いて『未来世代と共創するためには?』のパートでは、「“環境”や“共創”を前面に出すのではなく“かっこいい”や“楽しい”と直感的に魅力を感じてもらうことが重要」といった指摘が参加者の皆さんから挙がりました。
浜島さんは、「入口で共感を得ることは非常に大切。過去にリサイクル関連の施策で、工場の現場の方々が登場するコンテンツを発信したところ、多くの方に自分ごととして受け止めてもらえ、良い反応を得ることができた」と自身の経験も踏まえて同調しました。
根本さんも、「人は自分が思い描いた未来や世界しか受け入れにくいもの。また、共感できたとしても、それを行動に移すことには高いハードルがある。だからこそ、影響力や意欲を持ち自ら動ける人を、一人でも多く増やしていくことが大切」と語り、ひとりひとりの行動と、その数を増やしていくことの重要性を強調しました。

第3部は、登壇者から参加者の皆さんへ質問を投げかけ、皆さんの考えを共有する、対話形式のセッション。ここではその一例を紹介します。
<問> 自分ごと化できるように対話するにはどうすればよいか?
根本「“~すべき”“一般的には~”といった表現を一旦置いて、“~したい”“~でありたい”といった欲求ベースで話すルールを設定すると、より深い議論ができる。また日常の中で情報の種を探す習慣を持ち、定期的に対話の場を設けることが大切」
<問> 社内での取り組みを進める際、関心の温度差があることにどう対応すればよいか?
浜島「“誰に響かせたいのか”というターゲティングが重要。価値観の異なる人を動かすことは難しいため、興味を持ちやすい層に訴求することが効果的。また、良い取り組みを推進するだけでなく、問題のある行動をやめる仕組みや課税などのアプローチも選択肢として考えられる」

その後、参加者同士の交流会を経て、今回のミートアップは終了。
お集まりいただいたさまざまな業種の皆さんにとっても、これから未来世代へ向けたコミュニケーションを効率的に行なっていくためのヒントを見い出すことができたのではないでしょうか。
CNUDではこれからも、同じ想いを持つ企業、団体、個人の輪を広げていきます。