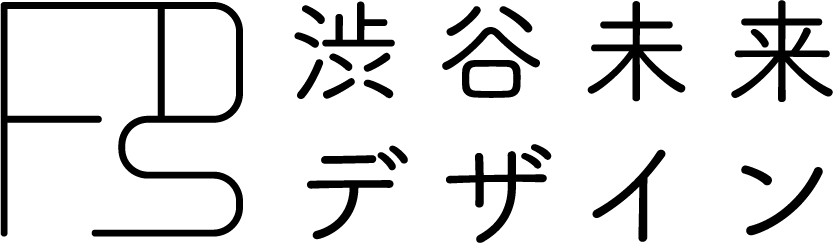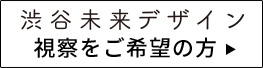渋谷未来デザインと一般社団法人SWiTCHが中心となり、脱炭素社会、生物多様性などサステナブルをテーマに産官学で議論をしてきた「Carbon Neutral Urban Design(CNUD)」。CNUDが定期的に開催している「CNUD START-UP PITCH」では、毎回テーマを設定し、その分野の環境先進スタートアップが登壇。登壇者が順にプレゼンテーションし、参加者からのQ&Aに答えます。登壇者どうしのトークセッションでは専門家ならではの問いかけに目からウロコの気づきも。最新テクノロジーを通して国際潮流をつかむ、気づきと交流の場となっています。
第5回目となる今回は「渋谷の熱中症対策」をテーマとして、国立環境研究所の岡和孝さん、SPACECOOL株式会社の宝珠山卓志さん、株式会社日建設計総合研究所の齋藤悠宇さんにご登壇いただきました。

CNUD START-UP PITCH Vol.5~渋谷の熱中症対策~
2025年4月25日(金) @ SHIBUYA QWS
<登壇>
岡 和孝(国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動影響観測研究 室長)
宝珠山 卓志(SPACECOOL株式会社 取締役CSO)
齋藤 悠宇(株式会社 日建設計総合研究所 不動産・データ戦略部門 研究員
佐座 槙苗(一般社団法人SWiTCH 代表理事)
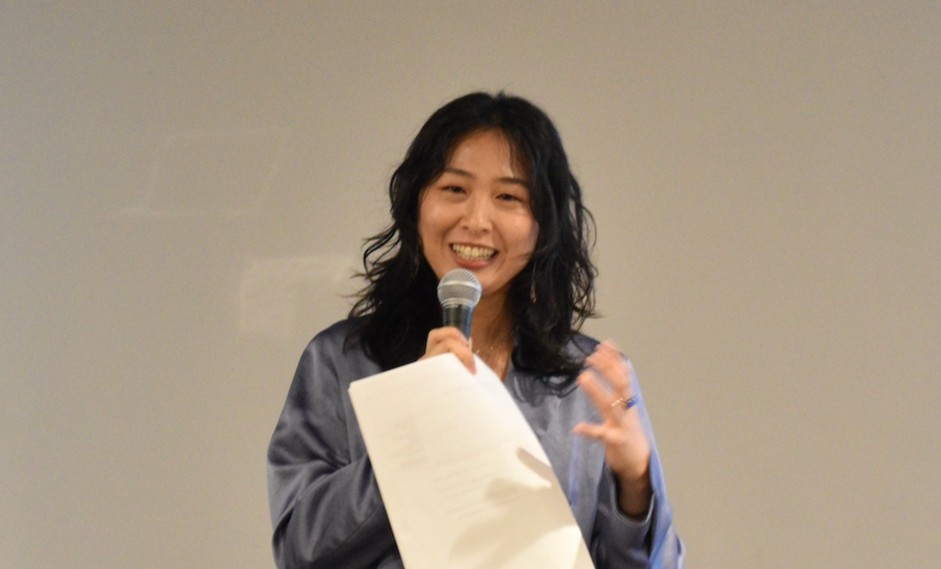
冒頭、本イベントファシリテーターの佐座から、渋谷など都市部で深刻化する猛暑とヒートアイランド現象を背景に、急激な気温上昇が高齢者や子どもの健康に及ぼす影響を指摘し会が始まりました。最新のデータでは、日本が気候変動対策の個人意識の面で低評価となっていることを取り上げ、従来の温室効果ガス削減(緩和)策だけでなく、熱中症対策など適応策の重要性が増していることを説明しました。
さらに、具体例としてプールサイドの白色塗装による温度低減や、通風の良い経路利用など実生活での熱中症対策を紹介。加えて、環境技術・循環型システムを推進するスタートアップによる新たな取組みを通じ、企業や自治体と連携した実践的対策の普及を訴えました。
熱中症と適応対策の現在


続けて、環境先進スタートアップによる3つのピッチが行われました。
まずは、国立環境研究所気候変動適応センター 岡さんによる「熱中症の現状と適応対策について」。
日本の夏の平均気温は100年あたり1.31℃のペースで上昇しており、東京などの都市部ではヒートアイランド現象により、さらに過酷な環境になっています。それを踏まえて岡さんは、国の対策として2021年に全国展開された「熱中症警戒アラート」や、2024年から導入された「熱中症特別警戒アラート」を紹介。特に後者は厳しい基準になっており、自治体にはクーリングシェルターの設置が義務づけられています。また、2025年6月から始まる、企業に対して従業員の熱中症対策を義務づける制度についても説明。
最後に、国立環境研究所 気候変動適応センターでは、民間企業や自治体と連携し、実践的な熱中症対策の支援や普及啓発活動に取り組んでいることが紹介されました。熱中症対策は「暑さを避ける」「水分をとる」という基本的な行動に集約されますが、それを実行するためには、個人だけでなく地域や社会全体での取り組みが必要であると締めくくられました。
<参加者との Q&Aセッション>

質問:科学的な適応のための知識やデータには、どのようにアクセスすればよいでしょうか?日常的に専門サイトを頻繁に見るのは難しいのですが、有効な情報源があれば教えてください。
岡さん「熱中症に関する情報であれば、環境省が提供しているLINEの通知機能などを活用するのが効果的です。地域ごとの暑さ指数(WBGT)なども確認できます。また、A-PLAT(適応プラットフォーム)では、将来の気候変化や熱中症リスクに関する情報が地図形式(WebGIS)でわかりやすく提供されています。」
質問:自治体が設置している給水スポット(水のステーション)や、学校のグラウンドを芝生にする取り組みは、熱中症対策として実際に効果があるのでしょうか?
岡さん「どちらも非常に効果的です。給水スポットの設置は水分補給の機会を増やし、熱中症のリスクを下げるうえで有効です。また、アスファルトの照り返しは体感温度を大きく上昇させるため、芝生化によって地表温度を下げることができます。他にも温度上昇を抑える舗装や塗料を使った道路整備も進められており、都市環境における熱ストレスの軽減に寄与しています」
先進的な放射冷却素材で世界を冷やす


続いては、SPACECOOL株式会社 宝珠山さんによる「放射冷却素材の現在と可能性について」。
太陽光を約95%反射しつつ、地表の熱を宇宙に逃がす性質を持つ特殊な樹脂で構成されているという同社の放射冷却素材について説明。この素材は従来の塗料と比べて高い反射率と放射率を持ち、昼間でも外気温より温度を下げることが可能。近年メディアや公共機関で取り上げられ、実証と評価が進んでいることを紹介されました。
また、この素材によって屋外に設置された様々な機器類の熱による故障を防げること、そして工場の屋根や、学校・病院などの屋上では空調効率の改善効果がみられること、業務用空調室外機に貼ることで電力使用量とCo2の削減効果があることや、畜産施設では生産期間の短縮が実現できることなど、温度低下による多様な効果を生み出すことができることを強調しました。
さらに、都市の表面反射率(アルベド)を高めることで、ヒートアイランド現象の抑制や地球温暖化対策への貢献も期待されており、国際会議で砂漠や北極地域などへの大規模展開も構想されていることを紹介。たった1枚の薄い素材が、世界的な環境課題の解決につながる可能性が示されました。
<参加者との Q&Aセッション>

質問:この素材の生産過程における環境負荷はどの程度なのでしょうか。廃棄時のリサイクル可能性についても知りたいです。
宝珠山さん「この素材はレアメタルを使用せず、簡易な製造工程により環境負荷が低いことも評価されています。廃棄時も産業廃棄物として処理されますが、有害なPFA類を使っておらず、他製品より環境への影響が低いです」
質問:反射素材をシート状ではなく、塗装やインクのような形で使うことはできないのでしょうか。その方が、用途が広がるのではないかと感じました。
宝珠山さん「塗装やインク化は一部の企業で試みられていますが、劣化が早いなど実用化に向けては課題があります。そのため、現在は耐久性の高い多層構造のフィルムとしての製品化を進めています」
質問:渋谷のような都市部でこの技術をどのように活用できると考えていますか。都市全体での展開の可能性があれば教えてください。
宝珠山さん「ビルの屋上などに放射冷却フィルムを広く展開することで、都市全体の太陽熱を反射し、ヒートアイランド現象の緩和が期待できます。また、太陽光の再帰反射フィルムとの組み合わせにより、さらなる冷却効果が見込めると考えています」
細かなデータ把握で熱中症リスクを自分ごと化


続いて、株式会社日建設計総合研究所 齋藤さんによる「高解像度熱中症リスクデータの開発について」。
株式会社日経設計総合研究所のチーム「HITS」が、2024年の東京都オープンデータハッカソンにおいて、熱中症リスクを可視化するダッシュボードを開発し、最優秀賞・オーディエンス賞を受賞したことを紹介。WBGTの指標に加えて、3D都市モデルを活用した日陰のシミュレーションを行うことで、きめ細かいリスク評価を可能にした点が高く評価されていることを強調されました。
このダッシュボードでは、東京都内の限られたWBGT観測地点だけでは把握しきれない、身近な場所の暑さリスクを、5mメッシュ・3時間単位で示しています。団地内外や通学路、公園などでの差を視覚的に示すことで、住民が「自分ごと」として熱中症対策を意識しやすくなることを目指しています。
さらに、人口分布や高齢者比率、救急車の配置、クーリングシェルターの位置などのオープンデータと組み合わせることで、行政や学校、地域団体が効果的な対策を立てることも想定されています。課外活動の場所選定や緑地配置の優先順位づけなど、実際のユースケースも多岐にわたっていることが説明されました。
<参加者との Q&Aセッション>

質問:このツールは誰が使うのが最も効果的だと思いますか?対象者について教えてください。
齋藤さん「主に行政の方に活用していただきたいと考えています。例えばクーリングシェルターの配置などの計画策定時に役立てていただけます。また、民間企業や自治会、住民の方にも使っていただきたいです。特に屋外活動を管理する立場の方にとって、熱中症対策の判断材料として重要だと思います」
質問:こうした情報を住民にどのように届ければ有効だと考えますか?
齋藤さん「行政は多くの情報をウェブサイトなどで発信していますが、住民がその情報を知っているとは限りません。情報を“自分ごと”として捉えてもらうには、見せ方が重要です。たとえば、『小さなお子さんがいる方に対して、子どもが受ける熱の影響は大人より大きい』という切り口から情報提供を始めると、具体的な行動(遊ぶ場所を選ぶ、データを確認するなど)につながりやすくなります。また、他の都市データと組み合わせて見せることも重要であると考えています」
先進的な技術をいかに社会実装していくか?

続いてのトークセッションでは、3者の刺激的なピッチを踏まえて、それぞれの立場からお互いの意見や質問が交わされました。
<『先進技術の社会実装に向けて』のパート>
Q.岡さん 「SPACECOOL社の放射冷却シートについて、非常にユニークな技術で、空調を使わずに温度を下げられる点に大きな可能性を感じます。夏場の高温が深刻な国や地域など海外展開も期待できるが、今後の具体的な展望を聞きたいです」
A.宝珠山さん「中東やアジアなど、より高温な地域からの引き合いはすでにあります。ただ、日本でも十分に効果がある技術なので、まずは国内で社会実装を進めつつ、輸出するのではなく現地生産・現地展開といったかたちも模索しています。日本の環境技術としてのブランド力も大切にしたいと考えています」
Q.岡さん 「齋藤さんらが手掛けたプラットフォームは、自治体の防災や都市設計への応用が進めば、全国的に大きな効果があるのではと期待しますが、様々な都市や地域への展開想定について伺いたいです」
A.齋藤さん「技術的には応用可能ですが、現時点でPLATEAUの3Dデータが整備されている地域が限られていることや、演算コストの高さが課題です。そのため、まずは関心のある自治体やパートナーと協力しながら、丁寧にモデルケースを増やしていく方針です。将来的には全国展開を視野に入れています」

<『気候変動適応に向けた身近な変化とは』のパート>
Q.齋藤さん「私たちは熱中症リスクのデータや予測、対策情報などを発信していますが、実際には利用者が少なく、なかなか活用されていない印象があります。人々が自分ごととして受け取り、行動を変えてもらうには、どのような工夫が必要だとお考えでしょうか?」
A.岡さん「人は単に情報を与えられただけでは行動を変えません。自らの生活の中で『この技術は自分にとって意味がある』と実感できる導線が必要です。例えば共感できる物語や具体的な利用シーン、他の人の使用例などを通じて、自然に使ってみたくなる仕掛けが求められます。『近所の高齢者が熱中症警戒アラートをきっかけに外出を控えて健康被害を防げた』といった具体的なエピソードや、家族の安全を守る行動と結びつけることで、 『使ってみよう』と自然に思えるきっかけが生まれます。技術と人間の接点をどうデザインするかが重要です」
Q.齋藤さん「中東では日差しを遮るシートを使って公共空間を快適にし、人が集まる場にしている例があります。日本でもバス停などの場所に放射冷却素材を活用すれば、公共のあり方に新しい展開があるのではと思っていますが、いかがでしょうか?」
A.岡さん「東京都でもバス停に放射冷却素材を使う実験をしていますが、横から熱風が流れ込むため、屋根だけでは効果が限定的です。ただ、広い空間で使えば十分に冷えることも分かってきています。今後は市場のような場所での活用や、建築基準と組み合わせて都市全体での展開が期待できると思っています」

以上、参加者同士のミートアップを経てイベントは終了。
世界的に気候変動が深刻化するなかで、その適応策についても、先進的な技術や取り組みによって大きな可能性が拓けてきていることが感じられる一夜となりました。
今後ともCNUDの活動へのご注目、そして積極的なご参加をお待ちしています。