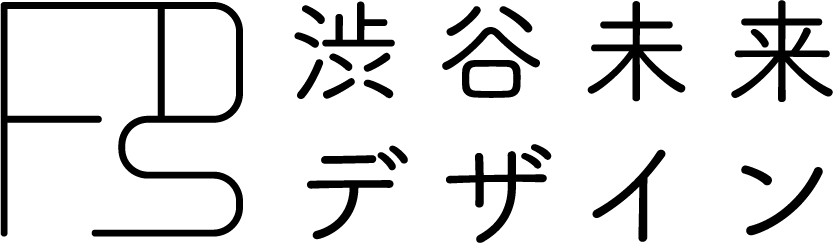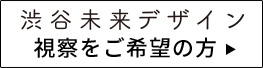ナプキンを通して女性の活躍を応援し「生理の貧困」に手を差し伸べる“安心”な社会を目指して
渋谷区と一般社団法人渋谷未来デザイン、そしてユニ・チャーム株式会社との連携により、2025年10月15日より、渋谷区内公共施設の女性用トイレへの生理用ナプキンディスペンサー設置に向けた実証実験がスタートしています。
ユニ・チャームでは、学校や職場での生理用品の常備化により学業や仕事に集中できる環境づくりを支援する「どこでもソフィ」プロジェクトを、同じく10月に始動。今回の渋谷区での取り組みは、それが「まち」と連携のなかで創出できる効果と可能性を探るものであると同時に、渋谷区として抱えている課題解決に向けた施策にもつながっています。
女性が安心して活躍できる環境づくりに向けてこの取り組みを進める、渋谷区総務部インクルーシブシティ推進課の高澤由美さんと橋本理奈さんに、今回の活動に込めた思いや展望をうかがいます。聞き手は渋谷未来デザインの長田新子です。


誰でも安心して生理用品を手に取れる環境づくり
長田:10月からスタートしている今回の取り組みですが、元々渋谷区としてはどんな課題感を持っていらっしゃったのか、あらためておしえてください。

高澤:大きくは女性活躍支援という視点がまずあります。加えて、いわゆる「生理の貧困」の問題もあり、誰でも安心して生理用品を手に取れる環境づくりが必要だと考え検討を重ねてきました。外出先や仕事先での急な生理に対応できる安心な環境がつくりたいというのが一点と、もうひとつは、経済的・環境的な事情で生理用品を手に入れることができないというような方のニーズを把握したいという狙いもあります。
渋谷区では、小中学校では生理用品を保健室などに置いて手に取れるようなかたちにしてきたのですが、全ての公共施設に置くというところまでは、やはりなかなかハードルが高く、どうしたらそれが実現できるかと考えていたところに、渋谷未来デザインさんとの連携でなにかできないかという話になりました。
長田:渋谷未来デザインのパートナーで、こうした取り組みをされているユニ・チャームさんに参画いただいて、官民連携での実証実験からスタートしていこうということになりました。

高澤:2025年10月15日から12月26日を期間として、区内の公共施設のなかから協力可能な施設と連携し、この実証実験を始めるに至りました。利用された方にはアンケートに答えていただいて、集まった意見を今後に活かしていきたいと考えています。
それと私たちの思いとしては、こうした取り組みを通して、渋谷区で過ごしている女性の皆さんに対して「応援しているよ」というメッセージが伝わったらいいなと思っています。
トイレに生理用品が当たり前にある安心感
長田:アンケート結果の集計はまだこれからのタイミングではありますが、実際にディスペンサーの設置が始まってみて、周囲の反応などは届いていますか?

橋本:トイレに行ったらナプキンが設置されているっていうのはやっぱり便利で、これからも使いたいという声はまわりの職員からも聞こえてきます。
高澤:例えば仕事をしていて、お手洗いに行くときに生理用品の入ったポーチを手にして席を立つと、「あ、生理なんだな」って思われちゃう、という不安がないという声もありましたね。たしかにそういうところで心理的な負担を軽減できるということもあるなと思います。
橋本:トイレでトイレットペーパーを使うように気にせず使える生理用品が、どこにでも当たり前にあるという環境がつくれたら、それは大きな安心感につながるだろうなと実感しています。
相談しづらい悩み事、小さな声を拾うきっかけにも
高澤:施設によっては、ディスペンサーにナプキンを補充するとすぐに無くなってしまうところもあれば、そうでないところもありします。イベントなどで多数の方が集まる時にはあっという間にディスペンサーが空になることもありますし、、場所ごとにニーズの度合いも異なってくるのはもちろんなのですが、ただ一概に人数の問題だけではないと考えるのも大切です。
たとえばひとりでいくつかナプキンを持っていった方がいたとして、もしかしたらその方は経済的に困窮されているのかもしれない。それをニーズと捉えて把握するために、アンケート結果から可視化できたら良いのではと思っています。
橋本:ですので今後の課題のひとつとしては、ディスペンサーの設置にあわせて、もし相談があったら区のこういう窓口に相談できますよ、という情報を添えるようなことができたらいいなと思っています。
高澤:例えば中学生くらいのお子さんで家庭の事情等で十分な生理用品を買ってもらえないという状況なら生理用品ですから、急場の対応ということでなく一週間分くらい必要であれば、ナプキン何枚かだけでは足りないですよね。本当に困っている方が必要な相談先につながるきっかけにもしていけるといいと思います。
長田:確かにそうですよね。安心して生理用品を手に取ってもらうことが目的だけれど、それを通して生理以外の問題——実は体調が良くないとか、もしかして家庭で何か問題があるとか、そういった外からは見えにくい悩み事の受け皿が、実はこういう窓口にあるんだよって、次の扉につなげていけるととても意味のあるものになりますよね。
実証実験の結果を踏まえアップデートを重ねていきたい
長田:ちなみに今回こだわったポイントのひとつとして、清潔感という意味での取りやすさもありますよね。下から引き出すタイプのディスペンサーや、ナプキン一枚ずつが個包装になっていることなど。

高澤:そうですよね。公共施設に置いてあるので、不特定多数の人が触るディスペンサーの蓋を触りたくないと思う方への配慮として、当センターでは蓋をあける必要がなく箱の下部からナプキンを引き出して取るタイプのディスペンサーを採用させていただいています。個包装に関してもやはり安心という意味で心理的に手に取りやすくなっていると思います。
長田:今後実証実験の結果を踏まえて、またそうした細かなところのアップデートも重ねながら、今後もこのプロジェクトを広げていけるといいですね。
高澤:はい。アンケートの結果を見て、実際の利用者の方々の気持ちを踏まえながら、どういうかたちで設置するのがいちばんいいのかというのは引き続き考えていきたいです。各施設のカラーによっては別の方法があるかもしれないですし、引き続きユニ・チャームさん、渋谷未来デザインさんと一緒に考えていきたいと思っています。

<編集後記>
公共施設のトイレに生理用品が「当たり前」に置かれる日。渋谷区を巻き込んだ官民連携により実現した実証実験は、その実現に向けた確かな一歩です。女性が安心して社会で活躍できる環境づくりの取り組みに、行政が関わることで、生理用品の提供のみにとどまらず、たとえば「生理の貧困」という顕在化しにくい社会課題の解決への糸口としての役割をも担うことができる——この取り組みが、多くの女性への「応援のメッセージ」として渋谷から確かなちからをもって広がっていくことを期待せずにはいられません。