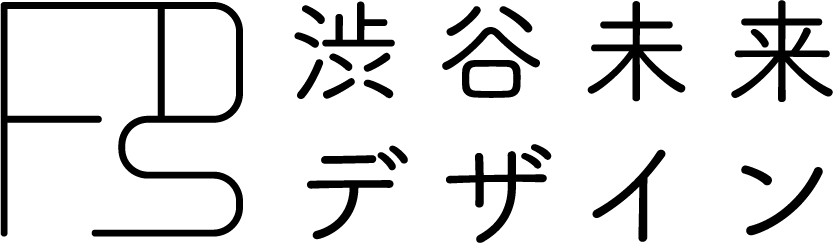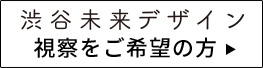“渋谷を舞台に ワーカーを盛り上げるコミュニティアプリ”『SHIBUYA MABLs(以下、渋谷マブルス)』。渋谷で時間を過ごすことの多い方の間で次第にお馴染みになってきたこのサービスの運営に携わる、東急不動産株式会社の大西里菜さんにお話をうかがいます。
24年4月に開業した東急プラザ原宿「ハラカド」の事業では、原宿のど真ん中とも言える場所で銭湯『小杉湯』のオープンに尽力し、そこで得たコミュニティの持つちからについての知見や、“まちと人”の関係性の捉え方の変化が、現在の活動にも大きな影響を与えていると大西さんは言います。
大規模再開発が進む渋谷のまち。その魅力をより豊かにしていくために、まちで暮らすたくさんの人の営みを支え盛り上げていくことも肝要です。人の暮らしとまちの豊かな関係、コミュニティというものが持つ可能性について、大西さんはどのように捉えているのでしょうか——
取材・文:天田 輔(渋谷未来デザイン)
写真:加藤圭祐
何者でもない自分で居られる、ゆるやかなつながり
大西さんが所属する「広域渋谷圏価値創造事業グループ」は、東急不動産のなかにあってまちのハードを扱うのではなく、ソフトの部分でまちづくりに携わりながらまちの魅力と価値を向上させていくことがミッションです。“100年に1度”の再開発で大きく変貌を遂げている渋谷。ハード面の整備が整い始めると、次に必要なのはそれを使ってまちをどう育てていくか、という視点です。
そんななか、渋谷マブルスが果たそうとしている役割はどんなものなのでしょうか。

大西「マブルスはひとことで言うと、都市で暮らす方々のコミュニティをデジタルも使いながら形成していくサービスで、今まだどこの都市にもない事例だと思っています。マブルスを使うメリットは大きく2つで、1つは『お得』。渋谷駅から2キロ圏内に到着してアプリでチェックインするとポイントがもらえます。たまったポイントは渋谷の200以上の加盟店でサービスや商品と交換できます。もうひとつのメリットは『つながる』。チェックインすることで今渋谷に誰がいるのかひと目で分かってメッセージのやりとりができたり、月に7〜8回くらいのペースでオフラインのイベントも行っています。オンラインだけでなくリアルでもつながれるのは大きな強みだと思います」
2年の準備期間を経てリリース後、1年ほどが経ったいま、「渋谷マブルスとしてやるべきことをやれば、ちゃんとユーザーのみなさんもそれについてきてくれる」と大西さんは今の状態に手応えを感じています。
大西「マブルスが目指している方向性のその先に、ユーザーのみなさんのニーズが確かにあると感じています」
マブルスに集まるユーザーのみなさんのたくさんの思いと向き合いながら、日々奮闘する大西さん。この仕事において、以前に携わっていたプロジェクトで得た経験値がとても大きく役立っています。それは、人と人との“つながり方”について、深く考えさせられた経験でした。
大西「高円寺で世代を超えて親しまれている銭湯『小杉湯』をハラカドに誘致するプロジェクトに携わっていたとき、なぜ若者が積極的に家庭のお風呂じゃなく銭湯に行くんだろう? と思ってたんです。でも小杉湯さんとのやりとりのなかで、まちの銭湯には“ちょうどいい距離感”があることを教わりました」
SNSなどオンラインだけでのつながりと、家族や職場といったとても近い距離感のつながり、「そのふたつしかない」と感じてしまうのがいまの時代性なのではと大西さんは言います。
大西「そのふたつの間の、ちょうど心地いい距離感。顔は知ってるけど名前までは知らないとか、仕事も肩書きも分からないけど銭湯に来たらいつも話す人たち、みたいな。自分のことを知らないからこそ話せることもあると思いますし。私もそれからは身も心も疲れたときには銭湯に行くようになりました(笑)」
まちの銭湯でのコミュニケーションに、仕事の肩書きは不要。どこの会社でどんな仕事をしているのかは関係なく、その人自身としてそこに居ることができる。銭湯の脱衣所で衣服を脱ぐのは、いわばひとりひとりが社会に立ち向かうための鎧を脱ぐのとおなじかもしれません。
大西「その学びはマブルスでもすごく大事にしています。いわゆる街コンのような出会いの場では仕事や年収などをすごく見られるでしょうし、ビジネスマッチングの場でもその人の会社名や役職がまず重要だったり…。そうやって、相手が自分に見合うかどうかの判断から始まるような出会い方ばかりなのを変えたいなと思って。そうではない心地いいつながりをつくっていける場というのは、本来まちが持っているべき機能だと思っています」
社会生活を送るうち、仕事や肩書きとは関係のない出会いが無くなっていくのは、誰しも共感するところかもしれません。また、初めて会った人を「◯◯社のXXさん」としてしか見ないことの、ある種の不自然さにも気付かされます。
大西「マブルスのイベントでは、何か目的を持って出会うのではなくて、ビジネスでもいいし、友達でもいい…目的は後からついてくるような出会い方ができる場づくりを心がけています。相手の肩書きが自分に見合うかどうかで人を見るのではなく、渋谷で同じようなマインドセットを持つ者同士ゆるくつながりましょう、というスタンス。ユーザーのみなさんからも、がっつりした出会い目的ではない自然体の人が多くて心地いい、ありがたい、という声をたくさんいただいています」

自分と異なる価値観を楽しめる渋谷民に
「渋谷の強さは、“ミルフィーユ構造”にあると思う」と、大西さんは学生時代から渋谷で過ごしてきた思いを話してくれます。
大西「私は青山学院大学で学んだので、キャンパスから出るとそこには渋谷で遊んでる人たちも、働く人たちもいて、働くといってもスタートアップから大企業まで、多様な職種の人たちがいますよね。たとえば道玄坂を歩いていても、一歩入ると異世界に思えるようなライブハウスがあり、その先にオフィス街が広がっている。そういった多様なレイヤーがミルフィーユのように重なっているのがこのまちの面白さだと思います」
渋谷に集まる多様な人たちがつくる多様なレイヤー構造。しかしそのレイヤー同士がすべてうまくつながり合えているわけではないことも、大西さんは指摘します。
大西「だからこそ、レイヤーに縦串を刺すようなことをマブルスで実現していきたいんです。業種も職種も肩書きも取っ払って縦でつながれたら。それができたら、渋谷は絶対もっと面白いまちになると思います」
渋谷が好きという気持ちを共通点にしてゆるやかにつながり合った、それまでは縁遠かった、多様な人たち。そんなつながりから生まれてくる未知のパワーを想像すると、とても魅力的に感じられます。
大西「自分とは違う何かに出会うという経験をたくさんしていくことが、いまとても重要だと思っています。SNSの画面には自分にとって興味のあるものしか出てこないし、まちに出ても駅と会社を往復するだけではなかなか新しいものごとには出会えないものです。でもマブルスのようなコミュニティに飛び込んでみると、自分とは全然違う価値観や暮らし方の人たちと出会って『わからない』と感じる、その感情がすごく大事なんです」
お互いが想像力をもって、『わからない』を乗り越えていくこと。それは渋谷区が掲げる『ちがいを ちからに 変える街』の実現にも欠かせないことなのでは、と大西さんは言います。
大西「それは言ってみれば“ノイズを楽しむ力”だと思います。自分の価値観と違うものに向かって飛び込んで、面白がってみる。それが渋谷マインドになったら、このまちですごく面白いことが起きると思っています。自分とは違うもの=ノイズを受容して楽しめるマインドを、コミュニティの力でみんなで養っていけたらいいなと思います」

最後に、大西さんの今後の挑戦について尋ねてみると——
大西「まずは渋谷におけるコミュニティ形成を全力で推進したいです。マブルスを渋谷に集う人々から愛されるサービスに成長させることが目下の目標です。そしてこのサービスを100年続けていくことがもっと大きな目標ですね」
そしていつか、コミュニティ形成とまちづくりに関する世界的なカンファレンスを渋谷で開催してみたい、という大西さん。渋谷マブルスがこれからもまちの人たちの暮らしに寄り添い、さらなる展開を見せていくことが期待されます。
異なる価値観を受け入れ、ときには思い切って飛び込んで楽しもうとするマインド。多様な人たちの暮らしが交差するまちだからこそ、渋谷が先進事例となって、ちがいを受容し合えるやわらかなつながりを育んでいく。そこから生まれてくるであろう大きな力と可能性を信じて、大西さんの奮闘はこれからも続きます。